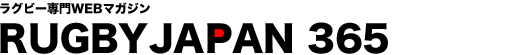8月7日、ラグビー日本代表、エディー・ジョーンズHCが都内でメディアブリーフィングに出席。この夏に行ったウェールズ戦を総括、さらに今後の強化についても言及した。
エディー・ジョーンズHC
――ウェールズ代表との2試合を振り返って?
ウェールズ代表とのシリーズから何を学んだか。4つのエリアがあります。
1つ目は、感情をどうコントロールするかというスキルを育成しないといけない。ウェールズ代表の2戦目で、感情的に正しいマインドを持つかというところが着目したところでした。やはり、若手からすると 2戦目に照準合わせるのは大変で、訓練が必要です。そこに着手していきます。
2番目はアタックのバランスですね。近年のラグビーは、空中でのコンテストが激化しています。各試合 30回、空中のコンテストがありますが、超速ラグビーを体現していかないといけない。キックを交えながらアタッキングゲームをしていかないといけない。PNCで発展させていきたい。

エディー・ジョーンズHC
3つ目はディフェンスの安定です。すぐに発表されますが、新しいDFコーチの下、容赦ないディフェンスのスタイルを確立していきたい。
4つ目は、リーダーシップを強化、育成しないといけない。ウェールズ代表では、リーチが戻ってきた。素晴らしい仕事をしてくれました。でも(キャリアの)終盤を迎えている選手で、毎回、最後だという気持ちでやっている。彼のリーダーシップなくなったところで、誰がそこを埋めるか。PNCでは、そこを強化、育成する絶好のチャンスだと思います。
ライオンズ対オーストラリアのテストマッチ、非常に楽しみました。特に2戦目、久々に素晴らしいテストマッチを見ました。コンテスト、継続性が素晴らしいバランスで、一方がモメンタムを失うと、相手チームが勢いを増した。
あの試合を見ると、オーストラリア代表の80%のポゼッションが右側だった。逆半分がなかった。左側には誰もいなかった。ボックスキックの重要性が関係していると思いますが、ジャパンがトップレベルで戦うとなると、あのような試合で競らないといけない。あのようなゲームでも崩して、オープンな展開にもっていかないといけない。今後のラグビーの発展は興味深いです。